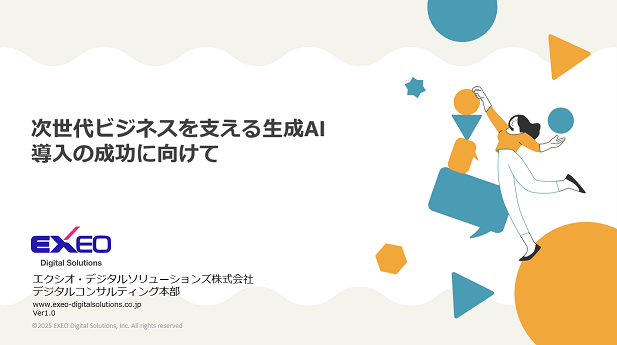生成AI導入を“本気で成功させたい”企業が頼る外部支援とは?

進化が著しい生成AI、これまで人が担っていた業務の一部をAIが代替・補完できる時代がきています。これは企業にとって業務の効率化や新しい価値創出のチャンスです。
しかし、生成AIは、スムーズに導入できるか、導入後はすぐに成果が出るかというと、そう簡単ではありません。実際には「どう自社に取り入れ、現場で活用すればよいのか分からない」「最新のAI技術を安全で効果的に運用できる体制が整っていない」といった悩みを抱える企業も少なくありません。
そんな中、生成AI導入を成功させている企業にはある共通点があります。それが、”生成AI導入を支援している社外の企業と連携”することです。今回は、こうした生成AI導入・運用を成功させるために必要な、社外パートナーの重要性と選定のヒントをご紹介します。
なぜ社外パートナーの支援が必要なのか?
生成AIの導入は、単なるITツールの導入とは異なり、業務プロセスの変革や組織文化のアップデートを伴う取り組みです。そのため以下のような理由から、信頼できる社外のパートナーを選定し連携することが必要になるのです。
専門知識と経験の不足
生成AIは急速に進化しており、モデルの選定や、既存システムとの連携・開発、セキュリティ対策など、多くの専門的な知識が求められます。社内にAI技術に精通した人材がいるケースはまだ少なく、他の技術に関しても社内人材だけで対応することが難しい現実があります。そこで専門知識が豊富なパートナーの知見を活用し、導入スピードや精度を格段に向上させることができるのです。
業務への適用ノウハウ
生成AIを業務に活かすには、単に技術を導入するだけでなく、業務フローにどう組み込むかが重要です。実績のあるパートナーであれば、導入事例や業種別の活用ノウハウを持っており、現場に即した提案が可能です。
特にパートナーが自社内での生成AI基盤の構築・運用を実践し、そこで得た知見をもとに他社支援にも展開している場合には、自らの業務にAIを組み込み、課題と成果を実体験しているため、表面的な支援に留まらず、実用に即したアドバイスや提案をしてもらうことができます。社内教育と定着支援
生成AIは、導入しただけでは効果を発揮しません。実際に現場の利用者が使いこなせるようになって初めて、業務効率化や価値創出につながります。このような場合にも、パートナーが社内向けの研修やマニュアル作成、FAQ整備などを通じて、現場への定着をサポートしてくれます。
継続的な改善と運用支援
初期導入時にうまく機能していても、業務内容の変化やユーザーの使い方によって、徐々に課題が出てくることがあります。導入後も、利用状況の分析、機能改善や追加などの改善が必要になります。こうした状況でも常にパートナーが伴走することで、継続的な価値創出が可能になります。
理想のパートナー企業を見極める5つの視点
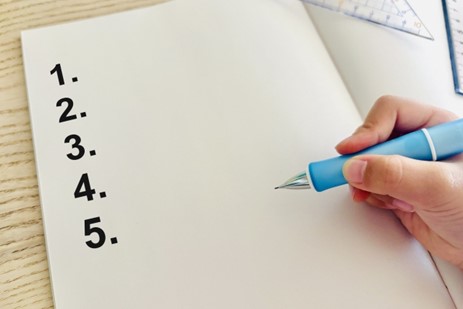
では生成AIの導入を成功させるために、どのようなパートナーを選べばよいのでしょうか?ここではパートナー選びのヒントを5つの視点からご紹介します。
技術・知見の提供やセキュリティ対応
まずは技術力。AI分野は技術進化が非常に速く、専門性も高いため、社内だけで最先端の情報やノウハウをキャッチアップし続けるのは困難です。複数のAIのソリューションを提供しているような、AIの専門家集団であるパートナー企業と連携することで、最新技術や業界動向をタイムリーに取り入れることができます。
また、企業で使う場合はセキュリティが最優先、社内データを扱う以上、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、安心して業務に使える環境を構築できるかが重要なため、AzureやAWSなどの信頼性の高いクラウド環境を活用し、企業のセキュリティポリシーに準拠したAI環境を構築できる技術力を持っていることも重要です。業務理解とカスタマイズ力
次に業務への理解力。生成AIは汎用的なツールですが、業務に即した使い方をしなければ意味がありません。たとえば、営業部門では提案書作成、カスタマーサポートではFAQ対応、マーケティングではコンテンツ生成など、部署ごとにニーズは異なります。
そのため、業種や業務内容に応じた活用提案ができるだけでなく、必要に応じてツールやプロンプトのカスタマイズに対応するなど、テンプレートを押し付けるのではなく、企業ごとの課題に寄り添ってくれる姿勢が大切です。導入前の検討や検証支援
導入前の「本当に使えるのか?」という不安を払拭するためには、検証が欠かせません。PoC(Proof of Concept:概念実証)やトライアル環境を提供してくれるパートナーであれば、実際の業務で生成AIがどれだけ効果を発揮するかを事前に確認できます。
このフェーズでの支援があると、社内の関係者も納得しやすく、導入後の展開もスムーズになります。PoCより手軽に実施できる簡易検証を無償で提供してくれる企業もあるので、まずは相談してみるのも良いでしょう。既存ツールとの連携
既存ツールとの連携の対応もポイントです。たとえば、Microsoft Teamsや他の業務アプリなど、日常的に使っているツールと生成AIが連携できれば、業務の中に自然にAIが溶け込んでいきます。
こうした既存の業務ツールとの連携性を前提に生成AIの導入設計をしてくれるのであれば、導入後の“使いやすさ”が格段に違います。社内展開のスピードも早く、実際に利用する現場からの抵抗も少なくなるでしょう。導入後の運用・改善支援
“導入して終わり”ではありません。むしろ、導入後の運用フェーズこそが重要であることから生成AIは“育てるツール”だと言えます。使い方の定着、利用状況のモニタリング、機能の改善や追加、社内教育など、継続的な支援が求められます。
パートナーは、導入後も定期的に利用状況を分析し、改善提案をしてくれる存在です。社内のAIリテラシー向上にも貢献してくれるため、長期的な視点での支援が期待できます。
生成AI導入支援を実施している企業のサポート内容ご紹介

ここで、実際の生成AI導入サポートの実施内容例として、エクシオ・デジタルソリューションズの『生成AI活用基盤提供サービス』をご紹介します。このサービスは企業が生成AIを安全かつ柔軟に活用できる“基盤”をワンストップで提供しています。
『生成AI活用基盤提供サービス』
◎お客様と伴走しながらサポート
導入検討から運用までトータルでサポートし、顧客の課題やユースケースに合わせた伴走型支援。
◎幅広いフェーズでのサポート
生成AI適用範囲の検討、PoC実施による効果検証、本格導入、運用設計、利用者向けの教育、活用促進まで幅広くカバー。
◎安心・安全な利用環境の提供
Microsoft社とのパートナーシップを活かし、Azure基盤により業務データも利用できるセキュアで安心・安全な利用環境を構築。SaaS型の提供プランも用意しており、すぐに利用可能な各種アプリケーションの提供や、個別ニーズに合わせたカスタマイズも可能。
◎導入後も継続サポート
利用者の教育やトレーニング、利用状況のモニタリング、継続的なサポートなど、導入後の運用管理も重視。
◎簡易検証(※)を無償で実施
初期検討段階では無償で簡易検証を実施し、生成AIの有効性や活用可能性を確認した上で次のプロセスを提案。
※簡易検証:自社業務における生成AIの有効性を短期間で検証できるサービスです。生成AI活用検討のファーストステップとして一般的なPoCよりもさらに手軽に実施できます。以下は簡易検証と一般的なPoCとの違いです。項目
簡易検
(エクシオ・デジタルソリューションズのサービス)
一般的なPoC
目的
自社の業務で生成AIが有効かを短期間で検証すること
業務適合性、技術面、費用対効果などを総合的に検証し、実用化の可能性を小規模に判断すること
コスト
無償(エクシオ・デジタルソリューションズ負担)
数十万円~数百万円規模の費用が必要
期間
約1ヶ月程度
一般的に1ヶ月~3ヶ月程度
検証内容
特定の業務に絞った簡易的な検証
業務適用性、技術検証、費用対効果など複数の観点から詳細な検証
成果物
検証結果レポート、次のステップの提案、概算費用の見積もり
詳細な検証レポート、試作品、具体的な数値を伴った評価レポート
リスク
費用負担がないためリスクは低い
一定の費用がかかり、検証規模によってはリスクが高まる
意思決定までの期間
検証終了後すぐに判断可能
検証結果を多角的に評価し、意思決定までに数週間~数ヶ月必要
適したケース
本格導入の前に、生成AIの有効性を手軽に確認したい場合
本格導入を前提として、多面的に慎重な検証をしたい場合
エクシオ・デジタルソリューションズでは以前より自社内での生成AI基盤の構築・運用を実践しているため、そこで得た知見をもとにした支援による実用に即したアドバイスや提案をしています。
まとめ
生成AIは、企業の業務効率化や価値創出に大きな可能性を秘めています。導入を自社で完結できる企業もあるでしょう。しかし、生成AIの力を最大限に引き出すためには、外部の専門家と“共創”するという方法も選択肢としては“アリ“なのではないでしょうか。
ツールの選定から業務への適用、運用後の改善までを一貫して支援してくれるパートナーとともに歩むことで、生成AIは単なる流行ではなく、企業の競争力を高める“武器”となるでしょう。
これから生成AIの導入を検討している企業にとって、最初の一歩は”信頼できるパートナーを見つけること”かもしれません。ぜひ、今回の5つの視点を参考に、理想のパートナー企業を見極めてみてください。
記事でご紹介したエクシオ・デジタルソリューションズの『生成AI活用基盤提供サービス』の詳しいサポート内容については以下の資料をご用意しました。よろしければ、ダウンロードしてご覧ください。
2025/10/01 | カテゴリ:AI
© EXEO Digital Solutions, Inc. All Rights Reserved.