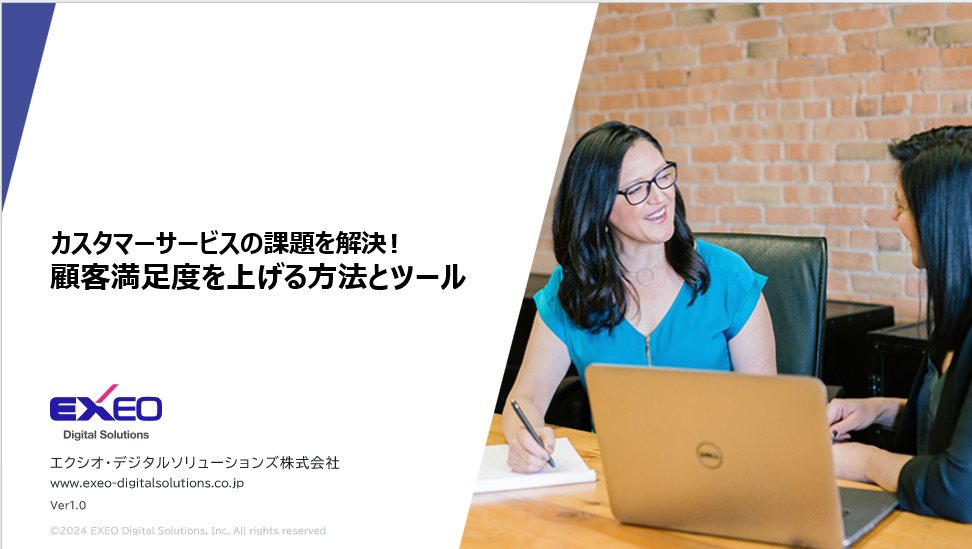API連携とは?できること、実装方法をわかりやすく解説

限られた予算や期間内でソフトウェア等の機能を拡張させたい場合、便利なのがAPI連携です。本記事ではAPI連携とは何か、さらに連携で可能になることとその利点、実装方法等をわかりやすく解説します。API連携について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
API連携とは?
「API」とは、「Application Programming Interface」の頭文字を取ったものです。 「Interface」とは日本語で「接点」や「境界線」を意味し、例えばコンピューターと人間の「接点」であるマウスやキーボードは「ユーザーインターフェース」となります。APIの場合も異なるものを「つなぐ」意味は同じで、インターフェースを用いて違うソフトウェア同士が、相互に情報等をやりとりするメカニズムのことを指します。
このAPIを使って別々のソフトウェアを連携し、機能やデータをシェアすることを「API連携」と言います。連携によって簡単に機能を拡張できるため、自社で一から開発する手間が省けます。
仕組み
API連携を行うとソフトウェアの情報および機能を、別のソフトウェアに容易に組み込めます。
例えばユーザーがあるWebサイトから情報をリクエストすると、そのサイトではなく組み込まれた別のサイトのAPIより、レスポンスが返信されます。これが一般的なAPI連携のメカニズムです。
具体例としては、オンラインショッピングの決済サービスが挙げられます。オンラインショッピングで商品を購入して決済する場合、サイト内に決済の仕組みがあるわけではなく、クレジットカード会社等とのAPI連携により決済が行われています。
他にもSNS等のアカウントで別のWebサイトにログインできたり、クラウドサービスによってスケジュールやタスクが管理できたりするのも、API連携によるものです。アプリケーションごとの隔たりを感じず、スムーズにサービスを使えるのが利点です。
このように、サービスに対するユーザーの満足度を高めるために不可欠なAPI連携ですが、各サービスや企業の枠を超えてデータのやり取りをするため、その構築には専門的なノウハウが求められます。こうした知見をパッケージ化した「プラットフォーム」を提供するベンダーも数多く存在します。API連携でできること
API連携はすでにさまざまなサービスに広く使われていますが、社内システムにも活用が可能です。例えば、ワークフローは発注申請や経費精算に利用されるシステムですが、電子決済システムと連携させることで、金銭の出入りを自動で記録できます。
また、近年はインターネットを介したソフトウェアサービスであるSaaSを利用している企業も多いでしょう。SaaSのAPI連携を行っていれば、データ移行をする際に一度データを取り出して入れ直す、という作業を回避できます。人的ミスが起こりやすく手間もかかる作業を省略することで、業務を効率化できます。
API連携のメリット
API連携を行うことで得られる主なメリットは4つあります。以下にそれぞれについて詳しく解説します。
開発コストの削減につながる
機能拡張を自前で一から行うとなると、設計や開発、テストといったステップを踏まねばならず、完成までにコストも時間もかかります。
しかしAPI連携であれば、既存のソフトウェアの機能を組み合わせて利用できるため、設計からテストまでの工程をカットでき、開発時間を短縮できます。さらに無料で提供されているAPIも多いため、大幅なコストカットも望めます。公開ソフトウェアのデータを活用できる
API連携を行えば、オープンになっているソフトウェアのデータを利用することも可能です。例えば、飲食店や小売店のWebサイトに地図が埋め込まれているのをよく見かけますが、これには地図APIが使われています。
他にも気象情報のAPIを活用すれば、Webサイトに天気予報等の情報も掲載できます。さらに2017年の銀行法の改正により、金融業界でもAPI開放が進みつつあります。現在、銀行のAPIは家計簿アプリや会計ソフト等との連携が可能になっています。
専門的な情報が必要なアプリケーションを作成する際、自社でデータ収集から行うと多大な時間とコストがかかってしまいますが、API連携を活用すれば正確な情報を迅速に取得することが可能です。これにより開発のスピードを速められるだけでなく、サービスの幅も広がります。セキュリティ向上につながる
サイバー攻撃やマルウェアの脅威からシステムや個人情報等を守るには、高度なセキュリティ対策が必要です。しかし自社で構築するとなるとコストも時間もかかるため、できる企業は限られてしまいます。
しかし、Google等の大手プラットフォームとAPI連携を行えば、連携先のセキュアな認証を活用できます。提携先のセキュリティ対策を借りる形にはなりますが、コストを抑えながら安全性の向上も実現できます。ユーザーの利便性を向上できる
API連携を行えば、ユーザーがいくつものサービスをシームレスに利用できるようになります。
例えば、初めてのWebサイト等にログインする場合、SNSやGoogleのアカウントを使用できれば、個人情報の入力も不要で便利です。また、オンラインショッピングのほとんどは別の決済システムと連携していることが多く、ショップ自体がカード情報等を管理しているわけではないため、セキュリティ面でも安心感があります。それにより顧客満足度の向上にもつながることが期待できます。
【4ステップ】API連携の実装方法

API連携を実装する際は、具体的にどのようなステップを踏めばよいのでしょうか。ここからはAPI連携までの4つのステップをご紹介します。
API連携で実現したいことを明確にする
まず初めにAPI連携の目的を明確にします。その際に、“業務効率化”といった漠然としたものではなく、「顧客管理システム(CRM)とMAツールを連携して、顧客情報を自動共有する」等、具体的なものにしましょう。
目的を具体化することで、連携に必要な機能も明確にできます。自社で開発しにくい難易度が高い機能を取り入れられるのも、API連携ならではのメリットです。連携先の選定を行う
API連携の目的や必要な機能が明確になったら、次に具体的な連携先を選定します。
APIの種類や連携することで得られる機能、利用料金等を比較検討し、最適な連携先を選びましょう。加えて連携先の実績も参考になります。ユーザーコミュニティがある等、利用者が多く実績が豊富な提携先は、実装や運用面もスムーズに行える可能性が高いです。
もし1つの連携先で目的を実現できない場合は、複数の連携先を組み合わせることも検討しましょう。連携先からAPIキーを取得する
連携先が決まればユーザー登録を行い、API連携の際に用いるAPIキーを取得します。取得方法は提携先によって異なり、場合によってはシークレットキーが発行されることもあります。
APIキーは利用者の識別や認証のために必要なものです。第三者に漏洩しないよう厳重に管理しましょう。公開されている仕様を参考にAPI連携を行う
APIキーやシークレットキー取得後は、連携先が公開している仕様に従ってAPI連携を行います。
実装後は必ずテストを行い、意図した通りの動作になっているかを確認しましょう。
API連携がカスタマーサービスの効率化に貢献
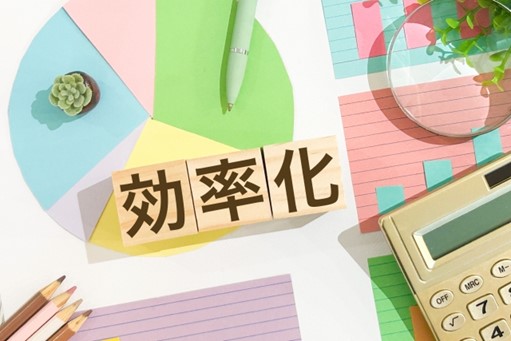
例えば顧客の名簿等を集約するCRMツールと、Webの閲覧履歴等を収集するMAツールをAPI連携させれば、顧客の属性に最適化したメール配信等のカスタマーサービスを効率的に実施できます。
あるいは、音声AIと問い合わせシステムのAPI連携によって、問い合わせ対応の迅速化とコールセンターの負担軽減の実現を図れます。いずれも、顧客満足度の向上に寄与する事例です。
さらに自動化やAPI連携によって、コミュニケーション窓口の集約化等を行うことで、問い合わせ対応の迅速化も実現します。その結果、顧客満足度の向上も期待できます。
ご参考資料:「カスタマーサービスの課題を解決!顧客満足度を上げる方法とツール」
API連携を実装する際の注意点
API連携は便利ですが、ソフトウェアの機能の一部を提供元に依存しているため、仕様変更等の際は大きな影響を受ける可能性があります。
仕様変更によって連携ツールが使用できなくなれば、業務が滞ったり、ユーザー離れが起こったりしかねません。
提携先を選ぶ際は機能や価格だけでなく、企業の信頼性や仕様変更時のルール等も確認し、よく検討して選ぶようにしましょう。
まとめ
APIによって異なるソフトウェアの機能を組み込めるAPI連携は、コストや時間を抑えて機能を拡張するために便利な仕組みです。対カスタマー向けのサービスだけでなく、社内システムにおいても、CRMやMA、コミュニケーションツール、自動化ツール等を連携することにより業務効率化を達成できます。
また、公開ソフトウェアのデータを使えたり、セキュリティ性能を高めたりできるのもメリットです。限られた予算や期間でソフトウェアの機能を効果的に拡張したいなら、API連携は効果的な手段であるといえます。
2025/04/21 | カテゴリ:アプリケーション・実⾏基盤
© EXEO Digital Solutions, Inc. All Rights Reserved.