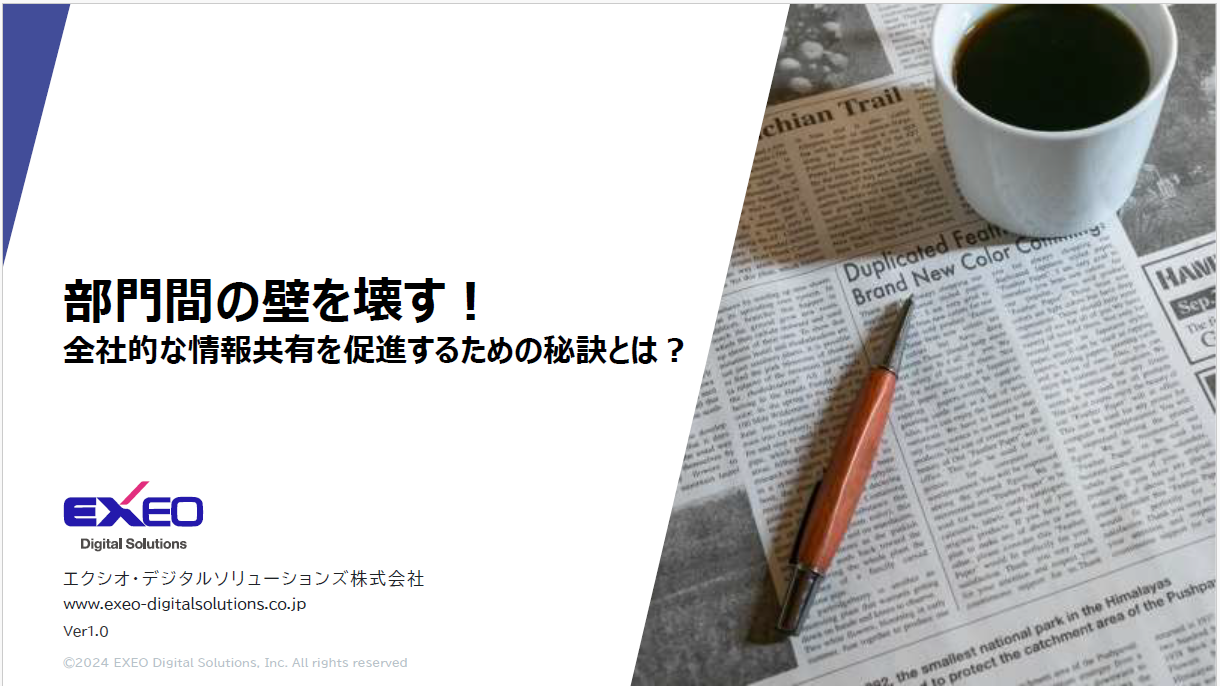システム運用とは?保守との違い、求められる運用方法について解説
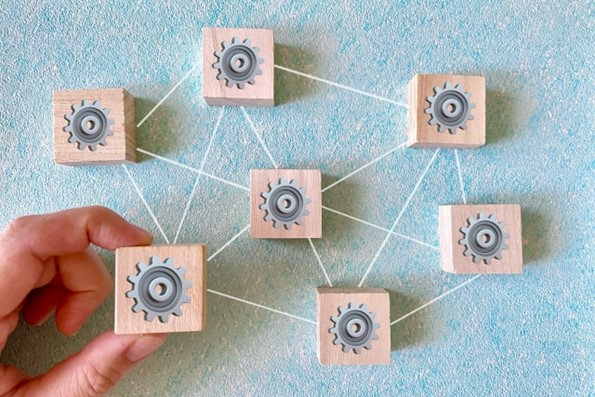
システム運用は、システムを安定的に稼働し続けるために必要な作業です。これからシステム運用に携わる方の中には、システム運用について知識を深めたい方もいるかもしれません。そこで本記事では、システム運用とは何かを知りたい方に向けて、システム運用の定義や業務内容の具体例等を解説します。記事を最後まで読めば、システム運用の基礎知識から最適化するための施策まで把握できます。
システム運用とはシステムの安定稼働を維持すること
システム運用は、システムを正常な状態に保つのに欠かせない業務です。この記事を読んでいる方の中には、システム運用と保守の違いが分からない方もいるかもしれません。システム運用に携わる場合は、システム運用の定義や保守との違いを押さえておくことが重要です。
以下では、これからシステム運用に携わる方や、改めてシステム運用に関する知識をおさらいしたい方に向けて、システム運用の定義や保守との違いを詳しく解説します。
システム運用の定義
システム運用とは、その文字からも意味が分かるように、システムの管理と運用を主とする管理業務のことです。システムの稼働状況に滞りがなく、その状態を維持し続けることが運用の目的です。社内システムの他にも、社外システムの管理と運用を任されることも少なくありません。
システム運用では、システム利用者が安全かつ安心して使用できるようにシステムを管理します。つまり、システム運用の担当者はシステム管理のスペシャリストといえます。
システム運用の対象になるのは、コンピューターシステムやソフトウェア等が挙げられます。システム運用の業務内容の具体例として、システムの稼働状況の確認や、トラブルが発生した際の対応等が挙げられます。この他、定期的なシステムのアップデートやバックアップ等も、システム運用が担う役割に含まれます。保守との違い
システム運用と混同されやすい業務のひとつに、システム保守があります。システム保守とは、稼働中の情報システムやコンピューターシステムのメンテナンス業務のことです。
主な業務内容は次章で解説しますが、一般的にシステムの不具合が出たときの修理や修繕、部品の交換や補充、整備等の作業が挙げられます。例えば、システムに障害や故障が発生した場合、システム保守の担当者が障害となる原因を究明し、問題を解決することでシステムを復旧させます。このようにシステム保守は、システムの障害や故障を未然に防ぎ、正常な状態を保つ上で重要な作業です。
一方で、システム運用は効率的な運用に欠かせない作業です。システムのパフォーマンスを監視したり、アップデートによってシステムを最適化したりする役割があります。企業の中には、システムの運用と保守の担当者を兼任させているケースも少なくありません。
【具体例】システム運用の業務内容
システム運用の定義や保守との違いが分かったところで、実際に現場ではどのような業務を担っているのかを見てみましょう。システム運用の主な業務内容は、大きく3つに分けられます。
・システム全体の監視
・トラブル発生時の記録や対応、原因の究明
・システムの運用方法の見直し
以下では、システム運用のそれぞれの業務内容について解説します。
システム全体の監視
システム運用の主な業務内容は、システム全体を監視することです。システムに異常が見られた場合は、システムからシステム運用の担当者に通知されます。監視対象は社内のサーバーやデータベースだけでなく、利用中のネットワーク等も挙げられます。他には、以下の監視業務も含まれます。
・アプリケーション
・ハードウェア
・トラフィック
・セキュリティ
システムを監視する際に用いられているのが、監視ツールやログ分析等です。監視ツールやログ分析等のITツールで、異常発生時に通知が届くような設定をすれば、システム内の異常をいち早く発見できます。トラブル発生時の記録・対処・原因究明
システムにトラブルが発生した際、ログ管理をはじめトラブルに対して適切な対応を取ることも、システム運用の業務です。そしてトラブル対応後には、トラブルが発生した原因を究明します。原因の究明によって、再発防止に向けた予防策を検討できますし、トラブル対応のマニュアルの作成や更新にもつながります。
他には、トラブル発生時の状況や対応方法等の記録を行う業務も、システム運用に求められる役割のひとつです。記録を取る主な項目としては、以下が挙げられます。
・トラブルが発生した日時
・トラブルの内容
・トラブルへの対処方法
トラブル発生時の一連の流れを記録することで、社内にナレッジを蓄積でき、同様のトラブルが起きた際もスムーズに対処できます。運用方法の検討
稼働中のシステムのより良い運用方法を検討することも、システム運用の担当者が担う役割のひとつです。例えば長期間運用しているシステムの運用方法を見直していない場合、業務が非効率的になっているだけでなく、運用コストも必要以上にかかっている可能性があります。
現状に合った運用方法を行えているか確認するためにも、定期的に運用方法を見直すことが重要です。システムの運用方法を検討する際は、最新技術やトレンドをリサーチし、自社にとって効果が期待できる運用方法かどうかを見極めることをおすすめします。
システム運用を最適化するための施策とは?

近年ではDXの推進やクラウドサービスの導入等によって、管理すべきシステムの数が増えてきています。そのような中、効率的に業務をこなすためには、システム運用の最適化が不可欠です。
最後に、システム運用を最適化したい企業の担当者に向けて、最適化するための具体的な施策を紹介します。自社のシステム運用の最適化を図りたい方は、ぜひ参考にしてください。
ITSM・ITOMツールの活用
ITSMとは「IT Service Management」の略称で、ITSMツールはITサービス管理に特化したツールのことです。システム運用におけるインシデントの管理や運用方法の変更プロセスを体系化できる等、便利な機能が搭載されています。システム運用における管理業務を一元化することで、業務効率化につながります。
一方、ITOMは「IT Operations Management」の略称で、ITOMツールはIT運用管理に特化したツールです。ITOMツールを活用することで、自社のITインフラ全体の最適化を図れます。
ITSMツールやITOMツールについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
ご参考記事:「ITSMとは?重要性からツールの種類・選び方まで徹底解説!」
ご参考記事:「ITOMとは?ITSMとの違いやできること、メリットを解説」部門間の情報共有の強化
システム運用の最適化を図るには、IT部門だけでなく、他部門との情報共有を強化する必要があります。各部署とスムーズな連携が取れれば、運用管理の負担を軽減できる上に、システムにトラブルが発生した場合も迅速に対処できるようになります。
例えば、情報共有に特化したツールを導入するのも有効な手段です。部門間の壁をなくし、情報共有を促進するための秘訣を知りたい方は、以下の資料をご利用ください。
まとめ
システム運用とは、システム全体の管理と運用を社内外問わずに行うことを指します。システム保守は、システムに障害や故障が発生した場合に、原因を取り除くことに主軸を置く業務です。対してシステム運用は、システムが正常に稼働し続け、利用者が安全かつ効率的に使用できる状態を維持する役割があります。
システム運用の効率化を図るには、ITSMツールやITOMツール等の便利なツールを活用し、他部門とのスムーズな連携と情報共有を行える仕組みを整備することが重要です。
2025/05/13 | カテゴリ:アプリケーション・実⾏基盤
© EXEO Digital Solutions, Inc. All Rights Reserved.